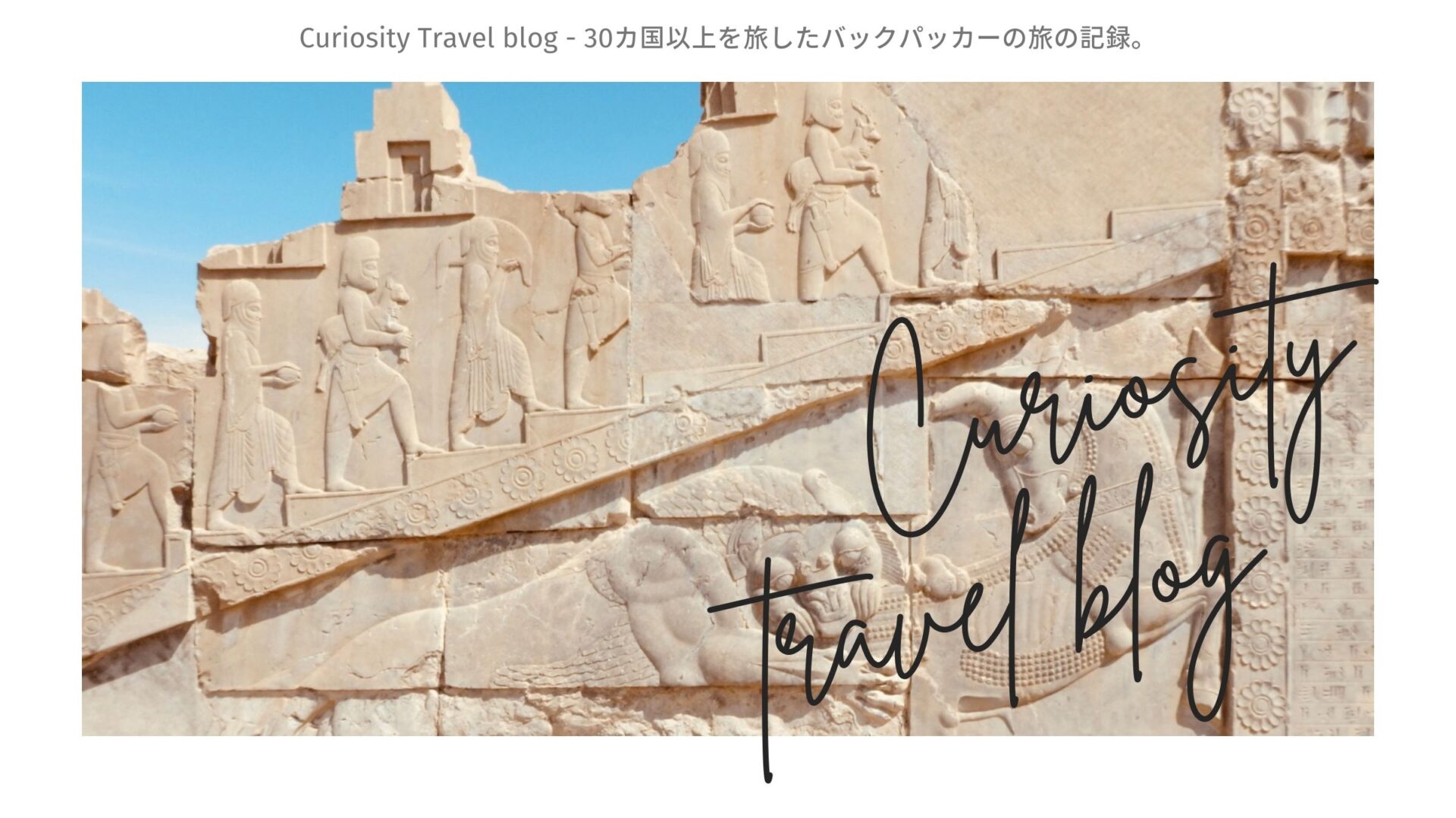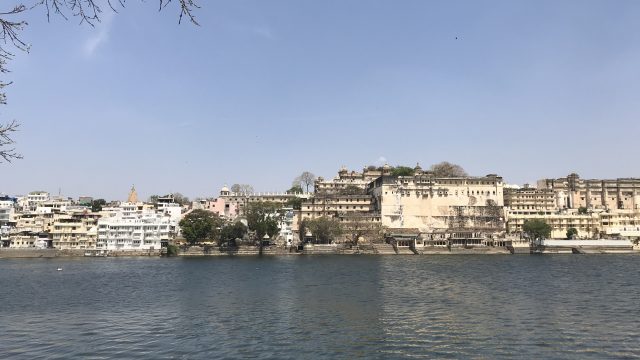2019年6月、バルカン半島の国々を巡る旅をしました。
その際、「ヨーロッパの火薬庫」とも呼ばれていたこの地域の複雑さを肌で感じました。
特に、コソボ・セルビアは戦争が終結してからまだ20年しか経っておらず、生々しくそれを感じました。(コソボに対して、まだ紛争のイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか)
20年というのはとても短いですよね。人々と話していても、毎回戦争や民族の話題になりました。観光名所を巡るだけなら、それらの悲しい歴史をあまり知らなくてもいいかもしれませんが、地元の人との交流するなら、コソボを訪れる前に少し予習しておくと良いかもしれません。
今回は、コソボという国について知っておいてほしいことをまとめようと思います。
コソボってどんな国?
コソボはマケドニア、アルバニア、セルビアに囲まれたバルカン半島の内陸国です。
首都はプリシュティナ、人口は約180万人(145位)、面積は約1万平方キロメートル(166位)の小さな国。
人口の約9割はアルバニア人、その他にはセルビア人等が暮らしています。

コソボの国旗は、このようなもの。
中央のコソボの地形の上に、6つの民族(アルバニア人、セルビア人、トルコ人、ロマ、ゴーラ人、ボシュニャク人)を示す6つの星が描かれています。
コソボでは、この国旗よりもアルバニアの国旗が掲げられているのを多く見かけました。アルバニア人はコソボで人口の9割を占めており、一般民衆の間では、国旗に準ずる旗としてアルバニア国旗が掲げられることが多いそうです。

コソボ紛争について〜たった20年前の国際的な戦争
ここでは、20世紀初頭の社会主義時代から現在までの、コソボの現代史をまとめていきます。
ユーゴスラビア連邦時代、コソボの地域はのセルビア共和国内に位置していました。
同じセルビア共和国内にあっても、現在のセルビアの地域にはセルビア人のセルビア正教会の信徒が、コソボの地域にはアルバニア人のムスリムが多く、彼らの間にあった経済的格差によってコソボ地域のアルバニア人の不満は高まっていました。
コソボ地域での人々の不満が高まっていた時に、東欧の旧社会主義国での独立運動が高まります。これをきっかけに、ユーゴスラビア内でも民主化の動きが高まり、1991年、ユーゴスラビア内戦に発展。セルビア共和国内の自治州であったコソボでも分離独立を求める声が高まりましたが、セルビア側はこれを拒否します。
そんな中、クロアチアやスロベニアなどの旧ユーゴスラビア諸国は独立を得ていきますが、コソボの独立はなかなか認められず・・・ユーゴスラビアが解体した後も、現在のセルビアによりコソボの独立は認められませんでした。
その後、コソボ地域のアルバニア系住民による独立を求める声はさらに高くなります。
そんな中、セルビアは1998年、コソボ地域にセルビア治安部隊を派遣、コソボ解放軍の掃討作戦を実施し、この時コソボ紛争が表面化します。
1999年、NATO軍は人道的介入として空爆を実施、紛争は国際問題に発展してい来ました。
2005年には国連の介入により戦闘行為は停止され、諸外国も加わりこの問題の解決の道を探すことに。そして2008年、コソボは一方的にセルビアからの独立を宣言。現在もコソボには、NATO主体のコソボ国際安全保障部隊(KFOR)が駐留を続けています。

宗教の違い〜コソボ紛争の原因

以前はセルビアと同じ共和国内にあった現在のコソボ。前にも述べたように、セルビア地域にはセルビア正教会を信仰するセルビア人が、コソボ地域にはイスラーム教を信仰するアルバニア人たちが多く生活しています。
この差はどうやって生まれたのだろうか?
もともと、コソボ地域にはセルビア正教会を信仰するセルビア人が住んでいたそうなのですが、14世紀、オーストラリアのハプスブルグ帝国がオスマン帝国との間の防衛に当たらせるため、コソボ地域のセルビア人たちに対してハプスブルグ帝国内に移り住むように呼びかけたことで、多くのセルビア人がハプスブルグ帝国に移住。セルビア人がいなくなった場所にアルバニア人が移り住みました。その後コソボの地域はオスマン帝国に組み入れられ、1913年にやっと再びセルビア領に回復しました。
昔、セルビア人が住み、修道院や教会などセルビア正教会にとって重要な場所が数多くあるコソボ地域。しかし、アルバニア人もこの地域に6世紀ほど暮らしている。6世紀といえばかなり長い期間ですよね。そのため、両者にとってもこの地は譲ることのできない重要な場所となっているようです。
今でも解決されない問題〜実際に感じたこと
戦ってはいない、と言っても、今でもセルビア・コソボの人々の間には、互いに関する疑い、怒り、が残っているように感じました。
例えば、とあるセルビア人にコソボのことを話すと、「あそこは危ない、絶対行くべきでない」と、かなり酷い言葉も織り交ぜながら彼からみたコソボのことを話してくれました。
また、コソボの人々は今でもアルメニアと一緒の国になることを願っており、とある街ではアルバニアとコソボが一緒になった国土が壁に描かれていたり、コソボ紛争の際に活躍したコソボ解放軍のマークを多くの場所で見かけました。
そんな風景を見て、表立って戦ってはいないけれど、まだ全てが解決されているわけではないこと、人々の間には悲しみと、怒りがまだ満ちていること、それを実感しました。
終わりに
コソボを旅して、コソボの国旗よりも多く掲げられているアルバニア国旗、やけに新しい家々(後で聞くと、戦争の時に焼き払われて最近建てられた家らしい)や、人々の生々しい記憶など、20年前まで戦争をしていたという現実を生々しく感じました。
現在では、外国人旅行者にとってはコソボはとても旅行しやすい、安全な国となっていました。美しい自然、歴史のある街並みなど、魅力溢れる国だが、訪れる際にはぜひ最近まで戦争をしていたこと、今でも解決されていない問題を抱えていること、を知ってから訪れてみてほしいなと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました♪
ブログ村への投票や、SNSのフォローよろしくお願いします
Instagram:@azusa_1111_
ブログ村 :にほんブログ村